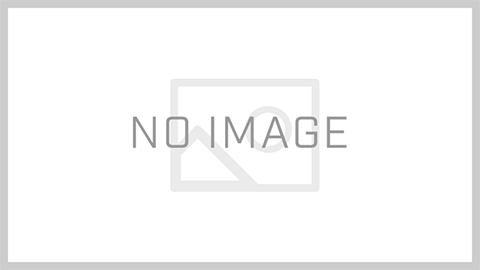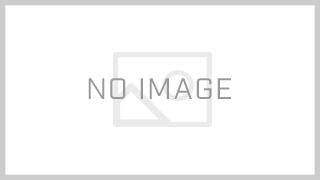「芸術の秋」「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」…etc.
なんでこんなに「○○の秋」が多いのか不思議だったのでそれぞれの由来を調べてみました。
こんにちは、そら(@15sora30)です。
「○○の秋」って四季のある国にしかない言い回しですよね、きっと。
「○○の秋」芸術の秋

「芸術の秋」の由来はおよそ100年前、
1918年に発行された雑誌『新潮』に「美術の秋」という言葉が使われたことが端を発し、
そこから派生して「芸術の秋」という言葉が生まれたようです。
二科展、日展、院展といった有名な展覧会が秋に集中しているのも「芸術の秋」という言葉のイメージを連想させたようです。
「○○の秋」食欲の秋

これはなんとなく想像つきますよね。
美味しいものがたくさん採れるから!
だと思って調べてみたらそれも正解だったのですが、
他にも面白い理由がありました。
夏のせい!!
その暑さなどから夏バテを引き起こして食欲が低下する人が多いですよね。
それが涼しくなってきて体調を整えやすくなり、
精神的にも安定するため食欲が増進させられるからなんだそうです。
冬のせい!!
夏の次は冬です。笑
冬になると食べ物が取れなくなります。
そのため秋のうちから蓄えを作っておこうという動物としての本能から。
冬眠前の熊と一緒、同じ考え方です。
このような2つの理由もあって食欲が増進させられる季節なので
「食欲の秋」
というようです。
「○○の秋」スポーツの秋

およそ90年前、
1927年9月25日発行の『朝日新聞』の見出しで「スポーツの秋」という見出しが使われたのが一番古い記録だそうです。
その後1964年開催の東京オリンピック、
その開会式の10月10日が「体育の日」と制定されたことで「スポーツの秋」が定着していったとのこと。
秋は運動しやすいですしぴったりですね。
「○○の秋」読書の秋

秋の夜長に読書を、なんていったりしますよね。
読書好きな私としては多くの人が読書に興味を持ってもらえるだけで嬉しい季節です。
灯火親しむべし
これは、中国の文人・韓愈(かんゆ)による詩であり、韓愈が息子に勉強(読書)をすすめる時に詠んだとされる詩で、「秋の涼しさが気持ちよく感じられ、灯りがなじむようになる」という意味なんだそうです。
つまり秋の夜長は、灯りをともして読書をするのに最適だという意味が込められているとのこと。
私の読書はもっぱら娯楽で勉強と呼べるものではないですけど。
また、日本では終戦後に「読書週間」が設定され、取り組まれてきたため徐々に「読書の秋」が浸透していったようです。
全く関係ないですけど、「読書週間に本を買ったら売上の一部を寄付」なんてキャンペーンがあったら気軽に参加できるなーなんて思っています。
以上私の調べた芸術の秋をはじめとする〇〇の秋という言葉の由来でした。
読書週間は終わってしまいましたがまだまだ夜長は続きます。
読書記録から気になった本を読んでくださったら嬉しいと思う今日このごろ。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
ブックマーク、コメント、読者登録、とても励みになります。
いつもありがとうございます。
秋の夜長にいかがですか。
<参考にさせていただいたサイト一覧>
スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋、その由来とは?(tenki.jpサプリ 2017年9月23日) – 日本気象協会 tenki.jp
読書、芸術、食欲、スポーツ…「○○の秋」の由来は? | 子供とお出かけ情報「いこーよ」
スポーツや読書に芸術「〇〇の秋」が誕生した由来を解説 – ライブドアニュース